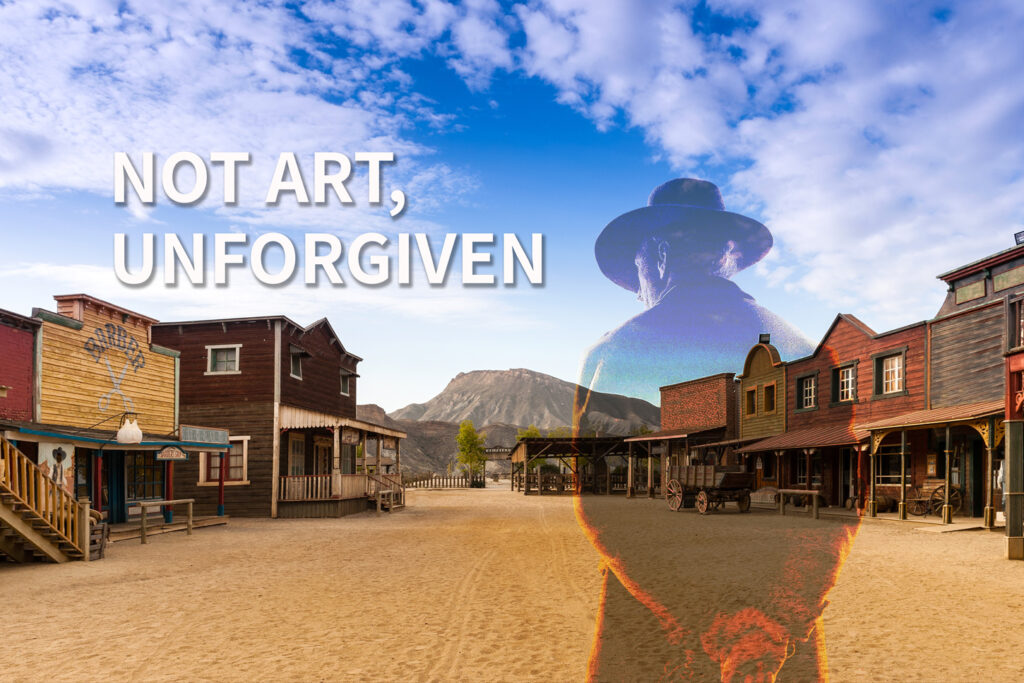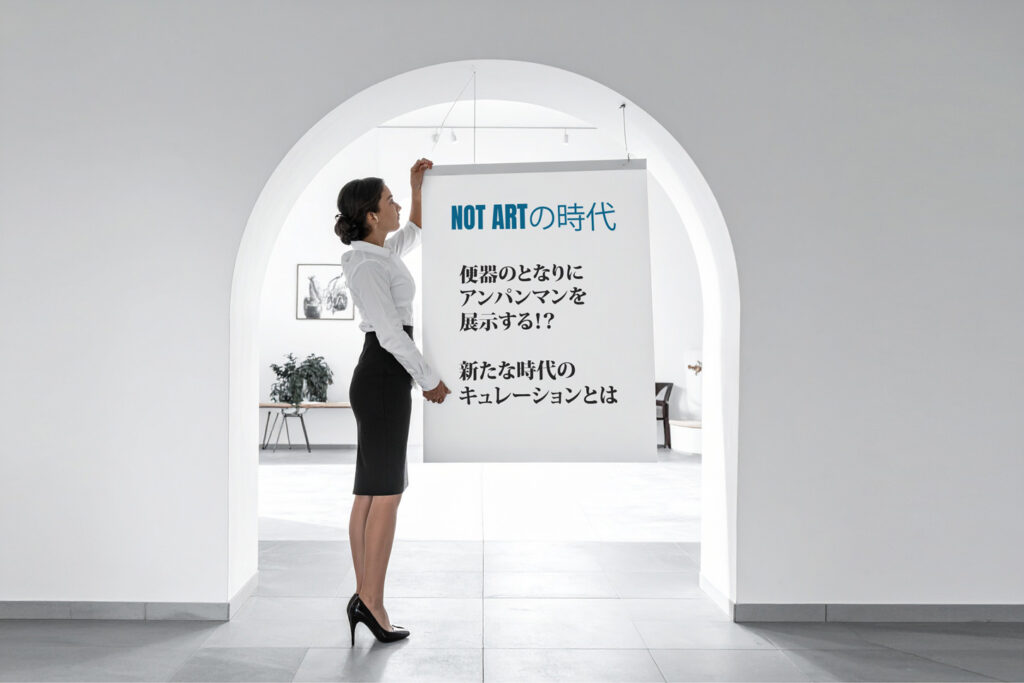現代アートの歴史からアートの未来を読み解く
「現代アートの歴史」と聞けば、専門書のように堅い解説を想像する人が多いでしょう。デュシャンの便器《泉》、草間彌生の水玉、バンクシーの落書き…。
けれども、私たちアートの専門家ではないものが、本当に現代アートを理解するために必要なのは、難しい美術史の専門書や美術館の壁にかけられた年表を読むことだけではない気がします。
そこで、ここではあえて、そうした美術史には出てこない、国民的キャラクター「アンパンマン」というNOT ART的存在を通じて、現代アートの歴史の流れを斜め読みしていきます。
(「NOT ART」というのはArtstylicの記事内で使う、現代アートの拡張ラベルです。)
やなせたかしが描いた「顔をちぎって人に与えるヒーロー」は、子供向け作品を超えた深い哲学を内包し、現代アートの問いと驚くほど響き合うのです。
👉 関連記事:実は誤解が多い「現代アート」という用語の定義から歴史の入り口を押さえましょう
現代アートの歴史は「否定」から始まる
デュシャンとアンパンマンの共通点
1917年、マルセル・デュシャンは《泉》と題した便器をアート作品として展示しました。当時は「こんなのはアートではない」と徹底的に否定されましたが、その後、美術史における革命と位置づけられました。
今、まさにNHKの朝ドラでも描かれているように、アンパンマンも誕生当初は「少し不気味」「カッコよくない」と人気を得ることができませんでした。
顔を差し出す行為は最初は「ギョッ」とさせられるし、ヒーローらしくないカッコ悪さが否定されたのです。
しかし、やなせたかしの思想「正義とは、空腹を満たすこと」という倫理観は、現代アートが挑戦してきた「常識を揺さぶる問い」と同質のものです。
ヒーローの顔が無くなってしまうというのは、それまでの常識を180度ひっくり返す衝撃で、大人心のついた子供にはもはや受け入れがたかったかもしれません。
しかし、そんなアンパンマンも、まだ大人のような固定観念を持たない純粋な小さな子供たちは、その優しさの本質に素直に触れて、徐々に人気を得て行ったことが、朝ドラでも描かれていました。
👉 関連記事:とりあえず歴史を早く知りたいというかたに(この記事と重複があります)
ポップアートとアンパンマンの大衆文化
ウォーホルの缶スープとパン工場
1960年代、アンディ・ウォーホルは日用品をアート化しました。キャンベルスープ缶やコカ・コーラの瓶は「消費社会の象徴」となり、大衆文化とアートの境界を曖昧にしました。
アンパンマンもまた、絵本からアニメ、映画、グッズ、テーマパークへと拡張し、子供から大人までを巻き込みました。
これは草間彌生の《かぼちゃ》が観光資源に変わるのと同様、アートと大衆文化の融合です。
👉 関連記事:とりあえず現代アートの潮流を知りたい方に
社会批評としてのアートとヒーロー像
ジョセフ・ボイスが唱えた「誰でもアーティストである」という思想は、アートを社会的実践に拡張しました。
アンパンマンもまた「空腹を救う」ヒーローとして、社会的弱者への眼差しを象徴します。
バンクシーが街頭で描いた壁画が「庶民のためのアート」であるように、アンパンマンは子供たちに寄り添い、大人にも深い問いを投げかけます。
👉 関連記事:
現代アートの課題と未来を示すNOT ART
現代アート史において、「これはアートではない」とされたものほど結果としては重要でした。
アンパンマンも「子供アニメ」とラベルを貼られていますが、そこに宿る思想・哲学は、単なる子供向けのかわいいマンガという枠を超えて、現代の深い病巣、分断の解決策を示すものであり、これからの現代アートが目指すべき課題と重なります。
「現代アート」という評価ラベルがどこで生まれるのかを知り、ラベルの無いクリエイションにスポットを当てることで現代アートの課題の解決策がみえてくるかもしれません。
👉 関連記事:「現代アート」というラベルを「NOT ART」に貼りかえる斜め読みの効果を説明しています。
分断と対話 ― 「許されざる者」と「アンパンマン」の共通点
アメリカではリベラルと保守の分断が深刻化し、現代アートはリベラル派のツールと見なされがちです。
しかし、その二項対立はアートの力を削いでいます。
映画『許されざる者』では、暴力と正義の二面性が描かれます。
アンパンマンも「戦い」と「自己犠牲」の矛盾を背負う存在であり、朝ドラでも度々でてきた「逆転しない正義」というテーマこそ、二項対立による分断を超える思想の象徴です。
👉 関連記事:多くの日本人が知らない現代アートの課題の本質に切り込む3部作
映画・音楽・アニメと現代アートのクロスオーバー
『ブレードランナー』は人間存在への問いを投げかけ、《イマジン》は普遍的な平和思想を提示し、ピンク・フロイドのライブやチームラボの作品は没入型体験を作り出しました。
いずれも現代アートが追求してきたテーマや形式と強く共鳴しています。
ここで注目すべきは、こうした表現を生み出したアーティストたちの位置づけです。
- リドリー・スコット(映画監督):『ブレードランナー』を通じて人間と人工知能の境界を問い、現代アート的な哲学を映画の枠組みで広めた。
- ジョン・レノン(ミュージシャン):《イマジン》で社会批評やユートピア的理想を音楽に込め、大衆文化を通じてアート的思想を普及させた。
- ピンク・フロイド(ロックアーティスト):ライブを総合芸術に変え、後の没入型インスタレーションの先駆けを築いた。
- 宮崎駿/スタジオジブリ(アニメーション監督):『となりのトトロ』『風の谷のナウシカ』などで自然観や人間の倫理を問い、世界中で美術館展示の対象ともなりながら、依然として「アニメ」として語られることが多い。
ただし、これらの表現が必ずしも美術館や批評の場で「現代アート」と同列に扱われるわけではありません。
映画は映画、音楽は音楽、アニメはアニメとジャンル分けされ、アートの正統的文脈に取り込まれる機会は限定的です。
この境界線こそが、アートと大衆文化を分ける見えない壁であり、「NOT ART」という独自ラベルを導入する理由でもあります。評価軸を変えて見れば、彼らの表現は現代アートと同じ問いを抱えているのに、必ずしも「アート」とは呼ばれてこなかったのです。
(そのような「アートエリートから得る格付け的ラベル」の必要が全く無いほど売れて大衆に支持されているから、でもあります。)
👉 関連記事:
SNS時代の現代アートと境界のクリエイション
SNSでは「宇宙猫」ミームのように、一瞬で拡散するビジュアル文化が大きな力を持っています。
アンパンマンもまた朝ドラで取り上げられ、世代を超えて大人の共感を呼び起こし、アートと大衆の境界を溶かす存在となっています。
まだ「現代アート」というラベルが付与されていないクリエイションこそ、私たちの日常の中にあります。SNSやテレビドラマといった大衆メディアに現れる表現は、本来「価値観の分断を埋めるNOT ART」であるべきです。
ところが現状では、SNSはむしろ価値観の分断を深めるツールとなり、オールドメディアもそのマイナス面を批判しつつ有効な対抗手段を見いだせずにいます。
だからこそ「相互否定の二項対立」にとどまらない、新たな社会的共感や相互理解を育む基盤が必要です。
その鍵となるのが「アンパンマンの精神」を受け継ぐクリエイションであり、まさに「NOT ARTの新しい拡散」が求められているのです。
関連記事:
まとめ ― パンの顔をちぎる行為と現代アートの未来
アンパンマンは単なる子供キャラではなく、現代アートの歴史を読み解く鍵です。
- デュシャン=否定から始まる
- ウォーホル=消費社会との融合
- バンクシー=庶民のための批評
- アンパンマン=自己犠牲と普遍的正義=分断社会への希望の光
すべては「NOT ART」から始まり、やがて現代アートのラベルを貼られて、その中核となりました。
現代アートの歴史をアンパンマンで斜め読みすることは、大衆と現代アートをつなぐ「NOT ART=未来のアート」の在り方を示す試みでもあるのです。
👉 関連記事:じっくりと現代アートの歴史を「NOT ART」の視点で斜め読みしてみたい方へ(徹底解説版)